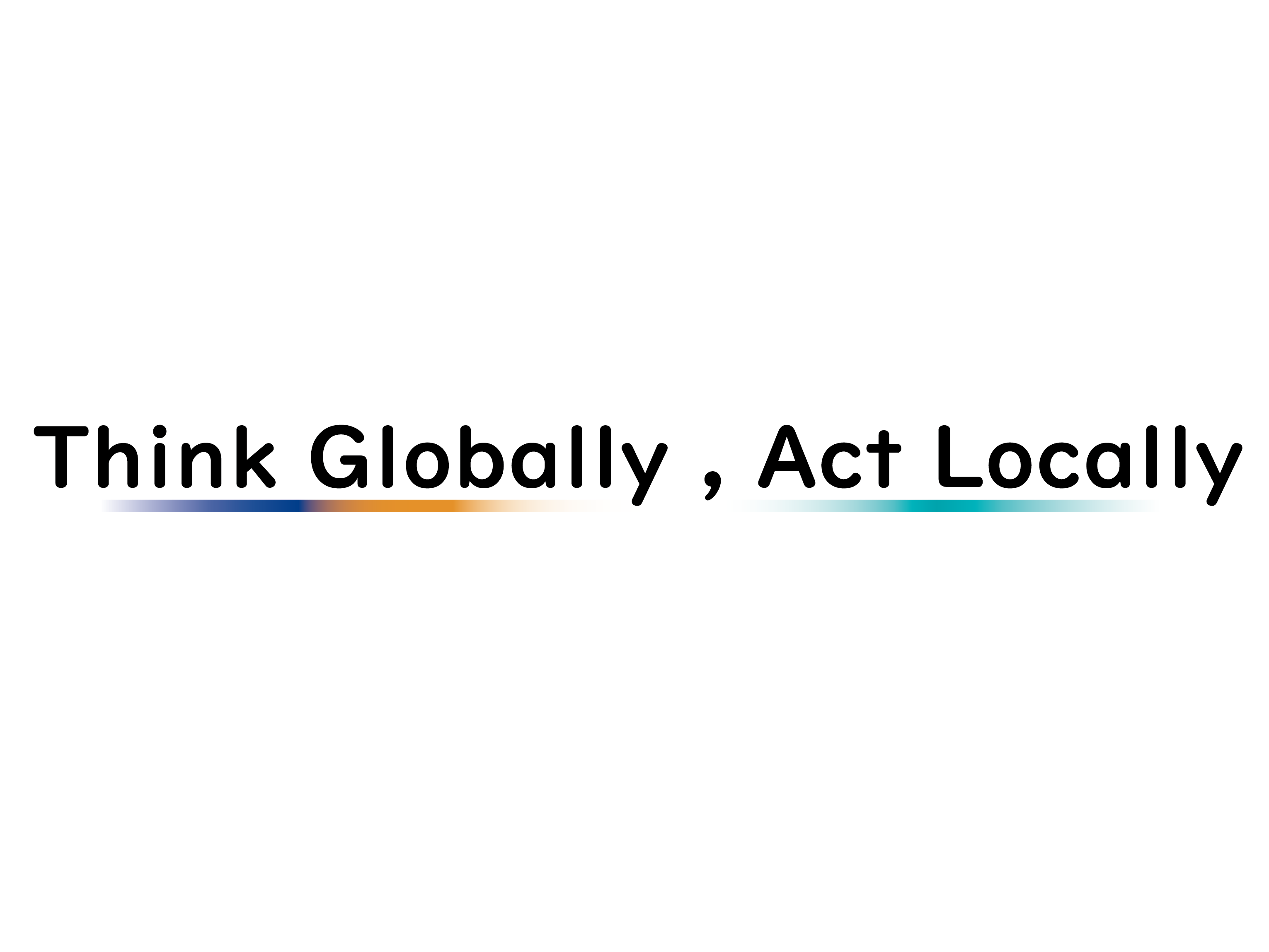西部カトリック大学 協定短期語学研修 体験談

体験談1. 派遣時:比較文化学科4年(2023年度夏期研修 参加)
体験談2. 派遣時:国際教育学科1年(2023年度夏期研修 参加)
体験談3. 派遣時:学校教育学科2年(2022年度夏期研修 参加)
体験談4. 派遣時:地域社会学科3年(2022年度夏期研修 参加)
体験談1.
○派遣時:比較文化学科4年(2023年度夏期(2023年9月)研修 参加)
はじめに語学研修の魅力についてですが、実際に行ってみて一番感じたのが異文化交流の楽しさでした。アメリカ、メキシコ、スペイン、韓国、台湾などいろいろな国からフランス語を勉強したい人々が集まっていて、フランス語や英語でたくさん話をしました。授業の後に公園でパーティーをしたり、夜はバーに行ったり、毎日とても充実していて楽しかったです。年齢も国籍もバラバラな人たちが1つの言語をきっかけにこんなに仲良くなれるんだ、と衝撃を受けました。
次にホストファミリーのあたたかさについてですが、私は滞在中に1度、一向にフランス語がわかるようにならない自分に嫌気がさし、悲しくてたまらなくなった時がありました。今思えばそれまでろくに勉強もしていなかったので当たり前なのですが、当時はあと2週間しかないという焦りや、どんどん上達していく周りの人たちと比べて劣等感を感じていたのだと思います。落ち込んで家に帰ると、ホストマザーはあたたかい言葉で私を励まし、おいしい食事を用意して、寝る前にあまいミントティーを淹れてくれました。ホストファザーは ”C’est pas grave. (大丈夫だよ)” が口癖で、ちょうどよい距離感で優しく見守ってくれました。私がフランス語をうまく話せない時も、遅刻しそうで焦っているときも、いつもにっこり笑顔で「セパカーセパカー」と言ってくれて、それは完璧主義でいつも自分を追い込んでしまう私にとって、お守りのような言葉になりました。フランスでの生活を通して、なんでも少し適当でいいこと、のんびり、自分の心に素直に従って生きることを教わりました。
最後に来年度の留学生へのアドバイスですが、私がフランスに持っていって良かったものは、虫刺されの薬・ファブリーズ・使い切りタイプの洗濯洗剤です。虫刺されの薬は公園で寝そべったり部屋の窓を開けていたりするとよく虫に刺されたので大活躍でした。ファブリーズと洗濯洗剤は、ホームステイ先のルールで洗濯が週に1回と決まっていたので重宝しました。コインランドリーは1回10ユーロくらいで高かったので家でこっそり手洗いしていました(笑)。
これからもフランス語の勉強を続けて、仏語検定2級に合格することが目標です。まずは5級からですが…卒論と勉強の両立を頑張ります。3週間という短い期間でしたが、4年生の最後にこんなに楽しい留学を経験できるとは思ってもみなかったので本当に幸せでした。一緒に行ってくれたみんな、応援してくれた人たちに心から感謝します。ありがとうございました!!
体験談2
○派遣時:国際教育学科1年(2023年度夏期(2023年9月)研修 参加)
私は今年の9月に、フランスの西部カトリック大学の短期語学研修に参加した。フランスのアンジェという町で過ごした三週間は、私に大きな変化を与えてくれた。今回、なぜ私がこの研修に参加したのかというと、高校生の頃からの目標であった、「大学在学中に、フランスに留学すること」を実現したかったからである。また、自分のフランス語のスキルをもっと磨きたいと考えていたことも、理由の一つである。
語学研修の参加が決定した後、留学の準備に向けて、ミーティングへの参加や様々な手続きを行った。大学生になって、親元を離れているという現状から、留学に関する手続きをすべて自分で行わなければいけなかった。例えば、航空券の振り込みや国際送金である。私は、国際交流センターの担当者の方々や一緒に語学研修に参加するメンバーに頼りつつ、すべての手続きを完了させることができた。そこで、今まで支えてくれた両親のありがたみを感じた。
アンジェでの三週間は、とても生きがいを感じた。幸い、私は東京大学から来ていた大学2年生の方と、ホームステイしていた。彼女は自分よりもフランス語が堪能であったが、私がホストファミリーと会話をする際には、いつも通訳として助けてくれた。そして西部カトリック大学では、フランス語のレベルが一番下のクラスに所属していたが、先生たちが授業を分かりやすく説明してくれたり、テストや授業態度をいつも褒めてくれたり した。クラスメートには、メキシコ人やアメリカ人、スペイン人などがいた。一人一人が異なった個性を持っていて、毎日の授業が本当に楽しかった。また、授業以外でも、自分から積極的にフランス語と英語を使って、様々な人々に話しかけることができた。
した。クラスメートには、メキシコ人やアメリカ人、スペイン人などがいた。一人一人が異なった個性を持っていて、毎日の授業が本当に楽しかった。また、授業以外でも、自分から積極的にフランス語と英語を使って、様々な人々に話しかけることができた。
学校以外では、アンジェの中心街に出かけることが多かった。フランスのカフェ文化に感動して、毎日新しいカフェを発見することが楽しかった。また、滞在して二週間後の週末に、仲間と一緒にパリに旅行をしたことも大切な思い出になった。みんなで力を合わせて、それぞれが行きたかった、ルーブル美術館やエッフェル塔などを訪ねた。どの場所を訪れても、やっと来ることができたという思いから、感動でいっぱいになった。
日本での生活が再開した今、私は明らかに自分自身の価値観や考えが変わったと感じている。なぜなら、大学卒業後の進路に対する考えに変化が起きたからである。今回、アンジェでフランス語を勉強し、フランスの文化に触れたことで、私はフランスで就職をしたいと思うようになった。また、フランスの大学院で言語と教育について勉強したいと考えている。そのためには、フランス語検定を受験するなど、フランス語の勉強を継続していきたい。
体験談3.
○派遣時:学校教育学科2年(2022年度(2022年9月)夏期研修 参加)
それは私にとって、最も素晴らしい人生経験のひとつであったに違いない。
私は今回8/28~9/26までの一か月間をフランスで過ごした。参加した理由は、フランスにおける教育に関心があり、それに付随する言語や国風はどのようなものか知りたくなったからである。出発前は不安の方が大きかった。それは初めての海外ということもあったが、なによりステイ先からのメールが来なかったのが一番の要因である。しかし、待ち合わせの駅に着くと、当たり前のようにmonsieurが出迎えてくれた。後で知ったがどうやらメールは確認しても返信しない性質らしい。そんなmonsieurの下で送ったフランス生活はとても驚いた。ホームステイは私1人だけだと思っていたのが、他に同じ日本人の学生、台湾からの留学生、ザンビア人、モロッコ人、カタール人と私のほかに5人もいた。ここはフランスだよな。と思いながらも、共通語はフランス語でそれぞれの国の文化や名物など知ることができとても刺激的で有意義な毎日を過ごすことができた。
街もどんなに素敵だったかわからない。Monsieurから借りた自転車で10分も走ると、1000年の歴史を感じさせる建物やレストラン、グランドシアターにお城、それに彩られたフランスの人々を一度に見ることができた。モンサンミシェルやサンマロなどにも行った。だが、私はこの街をぶらぶら歩きながら、道にせり出しているテラスである人は楽しく、ある人は真剣に話し合っているフランス人を見ているのが好きだった。
そしてさまざまな出逢いもした。どれも素敵な出逢いだったが、なかでも強烈に印象に残っているのが、大学の先生とPCR検査を一緒に受けた男性、ディズニーランドパリでの少女である。大学の先生は、教育学を専攻している自分にとって衝撃で新しい発見の連続だった。まず、すべての先生が元気ではきはきしていた。さらに、アイコンタクトや表情、全身で表現する姿は、今までの私のなかでの先生の概念を取り去るものであり 、ひどく感動した。驚いたこともある。それは先生が机の上に躊躇なく座りながらコミュニケーションを取っていたことだ。でも、嫌な気は全くしなかったどころかなにか先生の哲学を見た気がした。そして人のやさしさにも触れた。コロナ禍ということで私は入国時に使うPCR検査を受ける必要があった。病院には行けたのだが、説明されてもなにを言っているかを聞き取ることができなかった私を助けてくれたのが、ある男性である。一生懸命わかるように簡単な英語で説明してくれた。名前も知らない、たまたま出会った人。語学がわからないからこそ出会えた貴重な経験であった。全く話さずに出会った経験もあった。それはディズニーランドパリでの夜のショーのこと。音楽にのっていたらたまたま目の前にいた少女と目が合い笑顔になり、そのあとのショーは一緒に見たのである。まさに言語をこえた出逢いの瞬間だった。
、ひどく感動した。驚いたこともある。それは先生が机の上に躊躇なく座りながらコミュニケーションを取っていたことだ。でも、嫌な気は全くしなかったどころかなにか先生の哲学を見た気がした。そして人のやさしさにも触れた。コロナ禍ということで私は入国時に使うPCR検査を受ける必要があった。病院には行けたのだが、説明されてもなにを言っているかを聞き取ることができなかった私を助けてくれたのが、ある男性である。一生懸命わかるように簡単な英語で説明してくれた。名前も知らない、たまたま出会った人。語学がわからないからこそ出会えた貴重な経験であった。全く話さずに出会った経験もあった。それはディズニーランドパリでの夜のショーのこと。音楽にのっていたらたまたま目の前にいた少女と目が合い笑顔になり、そのあとのショーは一緒に見たのである。まさに言語をこえた出逢いの瞬間だった。
まだまだ書き連ねたいことはあるがいま思いかえすと毎日が笑顔だったように思う。今では完全に逆ホームシックになっている。これらの研修から学んだことは、積極性を失わずに挑戦すること、今のこの瞬間を大切に生きること。人とのつながりは素晴らしいこと、自分の視野が狭いということだ。最後になるが、この素晴らしい時間と空間を提供してくれたすべての人に感謝したい。
体験談4.
○派遣時:地域社会学科3年(2022年度(2022年9月)夏期研修 参加)
この研修に参加して、大きくまとめると次の三つのことを学んだ。一つ目は、人の温かさを実感したこと、二つ目は、なんとかなるまでの大変さ、三つ目は、海外での苦労である。一ヶ月の研修で素晴らしい仲間に出会い、貴重な経験をしたからこその学びである。
まず、この研修に参加しようと思った経緯は過去に海外に行ったときの後悔ともう一度挑戦したいという二つの気持ちがあった。ホームステイは今回が二度目で、前回の時は自らホストファミリーに話しかけれなかったこと、積極的にコミュニケーションがとれておらず、自分の不甲斐なさを痛感した。悔しい気持ちを持ちながら研修がスタートしたが、想像以上の壁があり、最初はとても苦労した。
フランスに着いてホストファミリーと対面した瞬間、全く何言ってるか分からず、現実を突きつけられ、本気でやばいと感じた初日。同じホームステイ先にはフランス語の話せる日本人学生がいた。彼に通訳してもらいながらなんとか乗り切った1週間目。すると、徐々にファミリーの言っていることが理解できるようになっていった。それでも、全て理解できた訳ではないので、ファミリーや彼が毎日優しく教えてくれた。コミュニケーションをとるには話すしかないので、返事しかできなかった受け答えがほんの少しずつ会話になっていった気がした。それもファミリーと彼のおかげである。彼らには1 番感謝している。
番感謝している。
コミュニケーションをとらなければ生活できなかったので、話そうとするが、なんて言って良いか分からず、理解できてるのに受け答えがわからなくて、必死に話そうと単語を並べた。下手なフランス語でも伝わったときはうれしく、ほんの少し会話に発展したときはとてもうれしかった。なんとか会話をしようと何度も試みたが、言い方が分からなかったりして、最後はなんとかなったのだがそれまでの道のりがとても苦労した。なんとかなるまでの難しさを痛感した。
海外で生活するときに1番苦労するのは、言葉の壁、次に文化の違いだと感じる。文化の違いに苦労を感じたことは滅多にないが、言葉の壁に関してはずっと苦労していた。言いたいことが言えず、話したいのに分からない、自分の力不足でもあるが情けなく思って、相手にも申し訳ないと感じていた。
私はフランス語を学んだ経験はなく、自分の中で留学は、話せるから行くのではなく話せなくても行くという考え方もある。その結果、周りの人は助けてくれ、コミュニケーションがとれたときの嬉しさはすごくある。話せた方が良いのは百も承知だが、話せなかったとしても終わる頃には成長を感じる。自分を信じて挑戦してみるのも良いかなと思った。