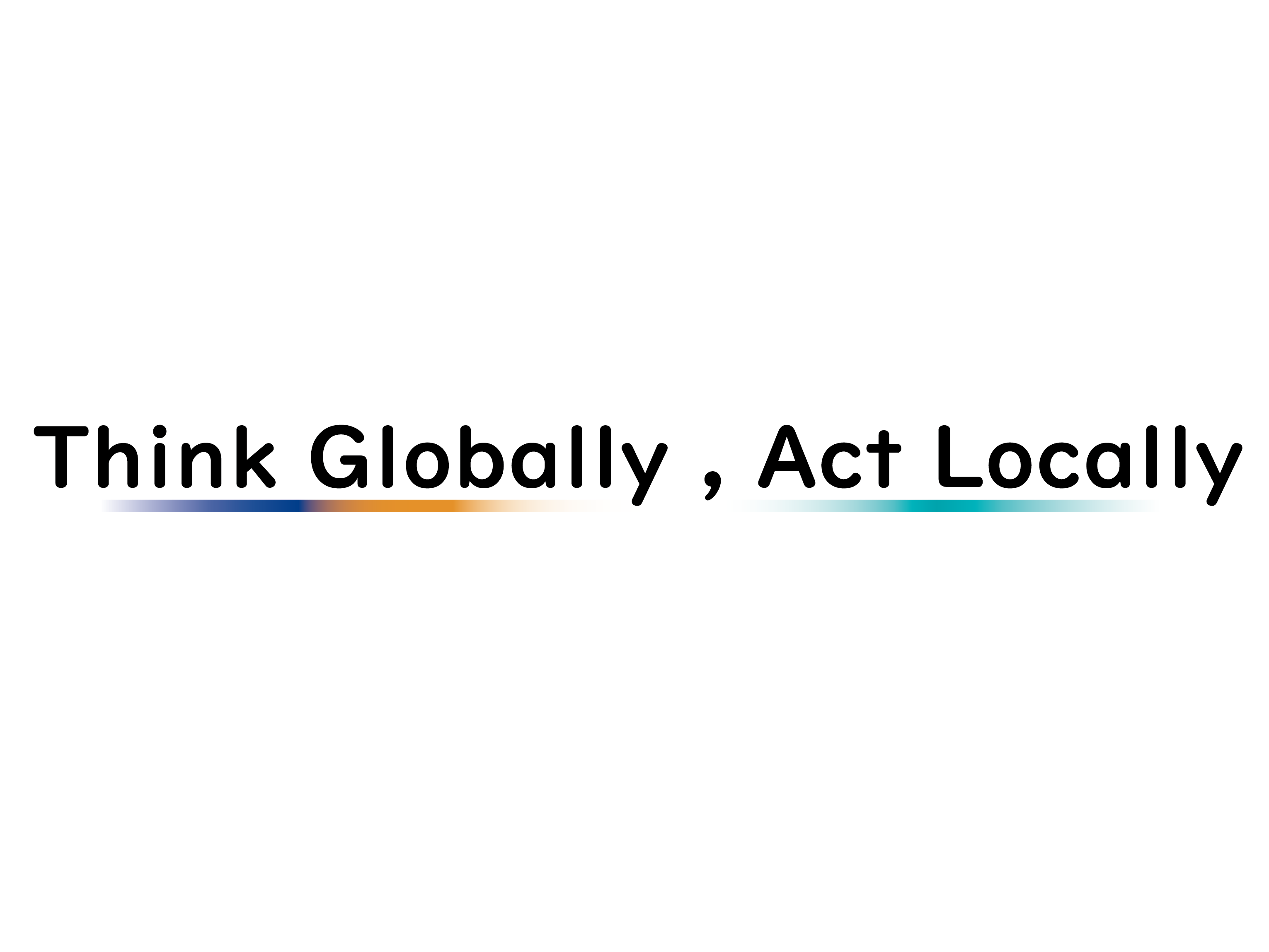ウィーン大学 協定短期語学研修 体験談

体験談1. 派遣時:比較文化学科3年(2023年度夏期研修 参加)
体験談2. 派遣時:英文学科2年(2023年度夏期研修 参加)
体験談3. 派遣時:地域社会学科3年(2022年度夏期研修 参加)
体験談4. 派遣時:地域社会学科3年(2022年度夏期研修 参加)
体験談1.
○派遣時:比較文化学科3年(2023年度夏期(2023年9月)研修 参加)
私は大学に入学してから、海外に行きたいという夢をずっと持っていました。ですがコロナの影響による規制などもあり、なかなか留学や旅行を計画から実行に移すことができず、1年、2年と経ってしまいました。3年生になった今からでも夢を少しずつ叶えていきたいと考えたときに、1年次に履修したドイツ語をもう一度学び直せる機会にもなる、この研修が私に合っているのではないかと思い、参加を決断しました。
今回の研修では3週間、年齢や出身も様々な10人弱のクラスメイトと一緒にドイツ語を学びました。内容としては以前大学で学んだことに近かったため、私にとっては復習が中心でした。ですが、その中でもオーストリアのドイツ語とドイツのドイツ語の違いなどを取り上げることが多かったことや、日本語ではなく英語かドイツ語で授業を進めていくことは大学では経験したことがなかったので、とても新鮮でした。また日本では、海外の人と接する機会が少ないので、ドイツ語を学びながら先生やクラスメイトと交流できたことは私にとって非常に有意義な時間でした。
授業は基本的に午前で終わるため、午後は自由時間でした。その時間に、博物館やスーパーに行ったり、スイーツを食べたりとウィーン市内でいろいろなことを体験できました。私はもともとオペラにあまり興味がなかったのですが、音楽の都とも呼ばれるウィーンでオペラを鑑賞して、はじめて面白いと感じました。また、この研修は3食自分で用意する必要がありましたが、同室の人と相談しながらスーパーで食材を購入して作ってみたり外食をしたりと時間に縛られることなく、食事が楽しめたことも、この研修で良かったと感じたことの1つでした。ドイツ語の学習だけでなく、日本では自分が体験するとは想像もしていなかったことをいくつも体験でき、自分の好きなことを増やせる貴重な自由時間でした。
ウィーン滞在中は、研修メンバーとスロバキアのブラチスラバと、ハンガリーのブダペストに行きました。2カ国ともオーストリアとは言語はもちろんですが、建物や料理など異なるところ共通し ているところがあり、比較することができ面白かったです。ブラチスラバは、ウィーンから電車で1時間程度で行くことができる距離だったため、日帰りで楽しむことができました。ドナウ川沿いにある「デヴィ―ン城」、建物の色が特徴的な「青の教会」、ブラチスラバ城など短時間で見て回れる場所が多い印象でした。最後の土日はバスを使ってブダペストで1泊しました。夜景を見たり、幼少期から夢であった海外の温泉「セーチェニ温泉」に入ったりと充実させることができましたが、見て回るには時間が足りなかったのでもう一度訪れたい国の1つになりました。半信半疑だったパスポートの確認などもなく簡単に国境を越えられるということを、実際に体験できたことも、この研修だからこそかと思います。スロバキアやハンガリーだけでなく、チェコやドイツなどのアクセスも充実していることも、魅力的でした。
ているところがあり、比較することができ面白かったです。ブラチスラバは、ウィーンから電車で1時間程度で行くことができる距離だったため、日帰りで楽しむことができました。ドナウ川沿いにある「デヴィ―ン城」、建物の色が特徴的な「青の教会」、ブラチスラバ城など短時間で見て回れる場所が多い印象でした。最後の土日はバスを使ってブダペストで1泊しました。夜景を見たり、幼少期から夢であった海外の温泉「セーチェニ温泉」に入ったりと充実させることができましたが、見て回るには時間が足りなかったのでもう一度訪れたい国の1つになりました。半信半疑だったパスポートの確認などもなく簡単に国境を越えられるということを、実際に体験できたことも、この研修だからこそかと思います。スロバキアやハンガリーだけでなく、チェコやドイツなどのアクセスも充実していることも、魅力的でした。
この研修を通して、改めてドイツ語の面白さを感じ学習意欲の向上につなげることができました。帰国後も学習を継続し、レベルアップした状態でオーストリアや今度はドイツの方にも訪れてドイツ語での会話に挑戦したいと強く思いました。また、ドイツ語圏でも英語を使える場面が多い中で自身の英語レベルの低さを痛感したため、ドイツ語同様に英語の学習も進めていきたいと感じました。自分を磨きもう一度訪れたいと思える体験ができ、さらに海外に行きたいという夢が広がった、この研修に参加できたことは本当に良かったなと思います。
体験談2.
○派遣時:英文学科2年(2023年度夏期(2023年9月)研修 参加)
私がこの研修に参加した理由は一年生の時に第二外国語としてドイツ語を学び始め、それらの授業がとても面白く、ドイツ語の力を伸ばしたいと思ったからです。現地の学校で勉強をすれば、日本で学ぶよりも実践的なドイツ語を学ぶことができるのではないかと考え参加しました。
私が在籍したクラスには、アメリカやロシア、ポーランドなど様々な国から、年齢や宗教の違う人たちが集まっていました。クラスの人数は12人で、そのうち3人が都留文科大学からの学生だったため授業でわからなかったところを質問したり、確認し合えたりすることができてとても心強かったです。授業は一時間に一回休憩が挟まれたため、集中力が切れることなく授業を受けることができました。授業は基本ドイツ語で進められていましたが、文法の説明や、語彙の紹介の際は英語での説明もあり、先生やクラスメートと会話するときは英語を使っていたため、ドイツ語を学ぶと同時に英語の勉強にもなりました。十三時に授業が終わり、課題は出ましたが午後は自由に時間を使うことができたので、観光地を訪れたり、カフェやスーパーに行ったりして過ごしました。通っていたキャンパスがウィーンの町の中心に近かったため、軽めに昼食を済ませて午後は 町の中心部で観光する、ということがとてもやりやすかったです。
町の中心部で観光する、ということがとてもやりやすかったです。
ウィーンはとても歴史のある都市であり、町の中心部は世界遺産に登録されています。町の至る所に教会や博物館、音楽ホールなど歴史のある建築物があるため、目的もなく町を歩くだけで楽しく、退屈することはありませんでした。また、美術史美術館を見学した際、キリスト教に関連した絵画が多く展示されていましたが、キリスト教の歴史や人物についての知識があまりなかったため、絵を深く楽しむことができませんでした。教会にもキリスト教に関係する場面を描いたステンドグラスがありましたが、どんな場面を表したものなのかわからなかったので、ウィーンに行くことを考えている人は世界史やキリスト教の勉強をしてから行くことをおすすめします。
三週間の研修はとても短く、ウィーンでやり残したことや行くことのできなかった観光地がまだまだあります。そのため、またウィーンに行った際に今回よりも楽しめるよう、さらにドイツ語を勉強しようと思いました。また、帰国後にコロナに罹ってしまいましたが、この語学研修では様々な貴重な体験をすることができ、良い思い出となりました。
体験談3.
○派遣時:地域社会学科3年(2022年度夏期(2022年9月)研修 参加)
ドイツ語を実際にドイツ語圏で学びたい、そんな気持ちを抱えつつ入学した都留文科大学にはドイツ語圏への留学プログラムがないことを知り、さらに新型コロナウイルスの影響により気軽に留学へは行けないという状況の中気づけば三年生になってしまった。そんな中、今年度からウィーン大学の三週間の夏期ドイツ語研修のプログラムを紹介していただいた。最初はドイツじゃないのか、と少し躊躇ったが伝統のあるプログラムに格安で参加できると言うことで、日本人にはあまり馴染みのない中欧の国際都市ウィーンへの渡航を決めた。
ウィーン大学のドイツ語研修はレベル別に分かれており、ドイツ語の知識がほとんどない人から上級者まで自分のレベルに合わせて誰でも参加できる。授業はすべてドイツ語で進められ、伝統あるプログラムなだけあって、三週間で確実にドイツ語を話すための型とドイツ語を聞き、理解する耳が鍛えられた。またドイツ語の授業以外にも、ピクニックやハイキングなど様々な文化やアクティビティのコースが課外で用意されており、各国からの留学生との交流やウィーンの文化に触れることなどができた。
学校がない時間は、寮でルームメイトと交流したりカフェ巡りをしたり、オペラや教会などをはじめとしたウィーンの文化に触れたりと毎日が刺激に溢れた楽しい時間だった。
またウィーンはチェコ、スロヴァキア、ハンガリーにアクセスしやすく、週末は更に自分をマイノリティな環境に置き、世界には素敵な場所がたくさんあるという発見や生活力のレベルアップを感じられた。特にドナウの真珠と言われるハンガリーの首都ブダペストはウィーンよりも気に入るほど魅力的でまた訪れたい。
今回の語学研修は歴史と文化、そして多様性に溢れた平和な都市ウィーンで、最高の仲間と共に終えることができた。ただ楽しいことだけでなく、言葉の壁や周りの学生の優秀さとのギャップを感じ、落ち込んで食べ物がのどを通らない時もあった。ドイツ語圏とはいえ、学生同志のコミュニケーションは基本英語なので、ある程度話せないとコミュニティの輪に入りにくく、悔しさを募らせる。海外に行く人は、どこの国に行くとしても英語を鍛えてから行くべきであると伝えたい。ただ英語はもちろん重要だが、EUでは依然としてドイツ語圏の経済などの影響は大きく、ドイツ語の学習は意義があるはずだ。
体験談4.
○派遣時:地域社会学科3年(2022年度夏期(2022年9月)研修 参加)
私は今回の語学研修についてドイツ語コミュニケーションの授業を受ける中で知りました。クラシック音楽が大好きな私にとってオーストリア、特にウィーンは小学1年生の頃からいつかは訪れたいと思っていた憧れの場所です。ネ イティブのドイツ語を生で聞いたことがなかったため、ドイツ語を実際の生活で使ってみたいという思いからも参加をすぐに決断することとなりました。
イティブのドイツ語を生で聞いたことがなかったため、ドイツ語を実際の生活で使ってみたいという思いからも参加をすぐに決断することとなりました。
念願かなってウィーンへ到着するとそこからは常に様々な発見が尽きない日々が初日から続きます。鍵を受け取って寮の部屋へ入ろうとするも何故かドアが開かなかったのです。それは日本なら鍵を入れて一回転させれば良いという感覚でいたためであり、ウィーンではあと二回ほど回す必要があったのでした。このように、ちょっとしたことから日本での生活との違いを体感し、次第にそれに慣れていくという毎日となりました。
ウィーン大学のクラスは先生を含め20人もいないくらいの少人数編成だったため様々な国(アメリカ、エジプト、コロンビア、ジョージア等)から集まった17~23歳くらいの年齢の生徒たちとはすぐに打ち解けることができました。授業では会話を実際にしてみるということが大切にされていたので常にコミュニケーションをとることができる環境にあったのも影響していたと思います。お互いに勉強しているドイツ語や英語を用いて自分の知らなかった文化について触れることができました。
授業は平日の9時から13時まででしたのでそれ以外の時間は自分の好きなように使えます。一緒に行った友達はチェコやスロヴァキア等近くの国へ行ったりもしていました。私の場合はウィーンが最も訪れたかった場所でしたので市内の散策が大半で、ずっと行きたかった国立歌劇場には週に3回訪れリーズナブルな立見席でオペラを楽しみました。目にするもの全てが新鮮で非常に充実した日々を送ることができ、とても満足しております。
ですが、私には心残りがあります。それはこれだけ毎日歩いたウィーンも見たかった場所をとても周り切れていないということです。そのため、いつか必ずまた来ることができるようにするためにもドイツ語の学習を継続し更に語学的余裕を持てるようにしていくことが私の当面の目標となります。